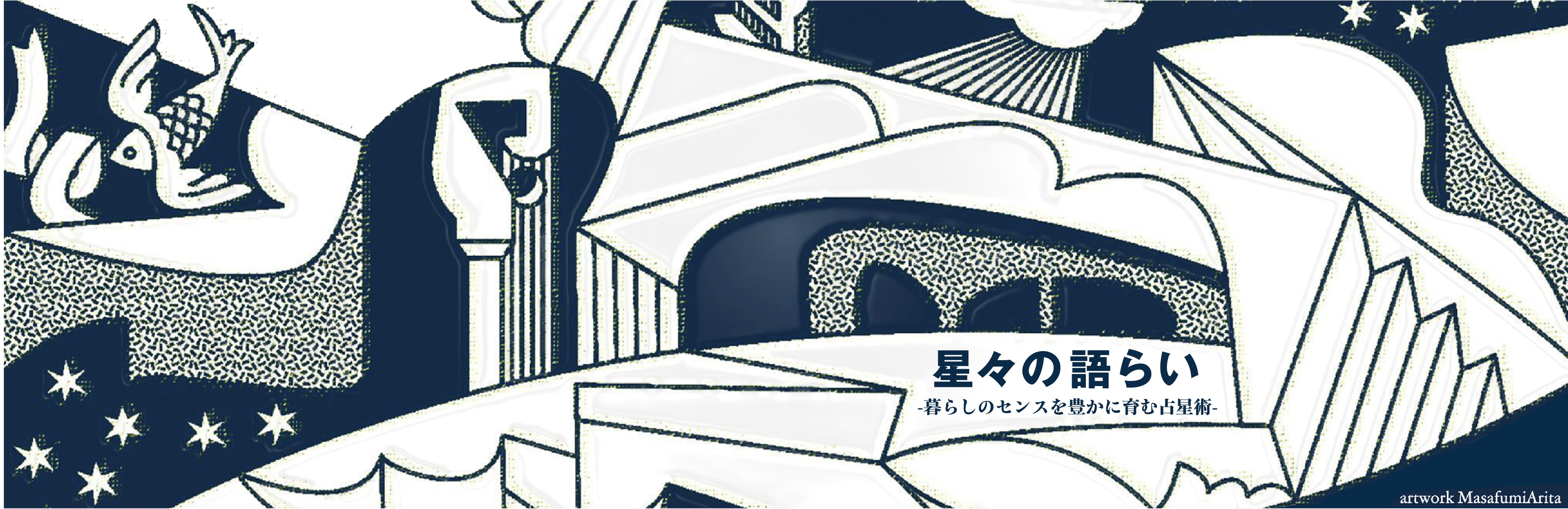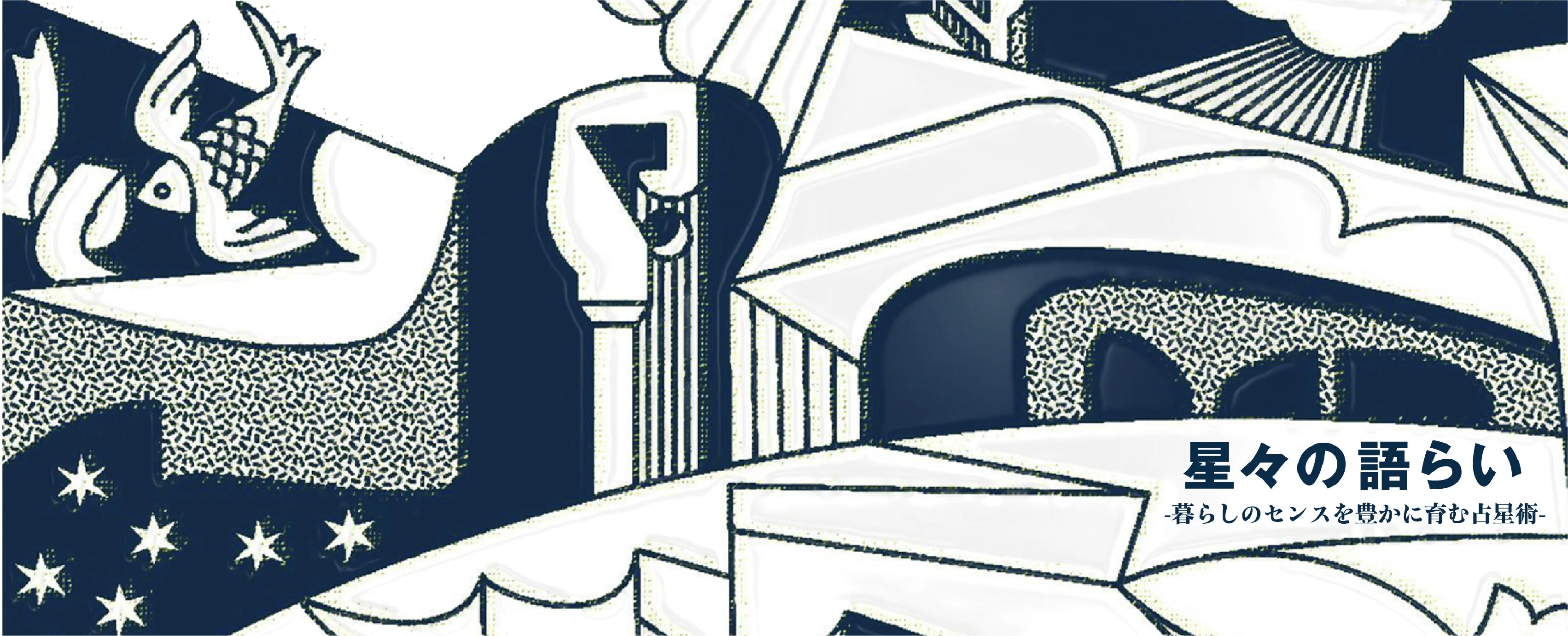INTRODUCTION
星に夢中になり始めたのは14歳のころ、当時(1980年)手描きで作成したホロスコープを眺めては、惑星が示す意味と同時代の出来事との共時性にワクワクしていたのを覚えています。
そのときの天体配置で特に印象的だったのは土星と木星が共に乙女座から天秤座に移動して約600年ぶりに風のエレメントに集っていたこと。
いまでは多くの人が耳にする「風の時代」へのストロークを感じながら未来の私らしい在り方を模索していました。
そこから半世紀近い月日を経た現在、新しい時代の到来は外からもたらされる以上に、個々の内なる気づきと豊かな繋がりから拡がっていくのだと実感しています。
この連載では、惑星たちが奏でる二十四節気ごとの天体配置から、より魅力的で私らしい暮らしを楽しむための星々の語らいをお伝えしていきます。
秋分・天秤座の季節
2025年9月23日
秋分は 昼と夜を等しく分かち合う一瞬
均衡とは静止ではなく 揺れながら結び直されるリズム
対立や差異の“あわい”に「調和」を見出そうとする季節です
私たちは“流れ”を生きているのに
いつの間にかそれを“線”で区切ってしまう
空に引いた目盛りの向こうで
世界は今も呼吸しているのです

秋分の太陽は天秤座の0度に立ち、
水瓶座の冥王星、双子座の天王星とともに
風のグランドトラインを描いています。
対岸に位置する牡羊座の海王星を加えると
大きなカイト(西洋凧)も浮かびあがります。
いずれも肉眼には見えない遠い星々ですが、
その見えざる響きは古い思い込みを深層から解体し、
新しい基盤をかたちづくろうとしています。
これらのプロセスは決して滑らかなものではありません。
逆行する星々と巡航する星々が織りなすスクエアは
私たち一人一人の生活や意識の細部にまで、
長期的な更新作業を示していそうです。
それは、硬直したものを解きほぐし、
新しいリズムを取り戻すための
揺らぎなのかもしれません。
宇宙は天宮図のように静止しているわけではなく、
太陽系は銀河をめぐり、地球もまた絶えず回転し続けている。
同じ天体の下にいても、体験や心の響きは人それぞれ。
時代の大きな流れをどう意識するかによって
それぞれの世界線が現れてくる。
新旧せめぎ合うなかで、
未来から降り注ぐ新しい直感に身を委ねることも
必要になるかもしれません。
例えば、秋の散歩道や新しいアートや音楽に触れるなど
視界の広がりとともに心も笑みを取り戻し、
揺れる天秤のバランスが調整されるように、
新しい時代のリズムへと導いてくれるでしょう。
ここで思い起こしたいのが、天秤座生まれの哲学者、
アンリ・ベルクソン(1859–1941)です。
彼は時間を線のように区切るのではなく、
持続(durée)する流れとして捉え直しました。
私たちが測りやすく細切れにしてきた時間の奥に
分割できない質的なリズムを感じていたようです。
私たちの“いま”は点ではなく、
過去が静かに浸み出してくる厚みであり、
未来へと延びていく流れの中にある。
そこでの記憶は脳の中に保存されるのではなく
意識の持続そのものに属すると考えました。
脳は倉庫ではなく、
行為のために記憶を選び直す
羅針盤のようなものだ、と。
そして日常で行われる判断の瞬間には
「これまでの私」がすべて参加している。
これをベルクソンは自由と呼びました。
彼にとって自由とは選択肢の計算ではなく、
過去と現在が重なり合って新しい流れを創りだす出来事なのです。
こうして見ると、
ベルクソンが語った「厚みのある現在」は、
秋分の星々の配置にも
映し出されているようです。
星は図式に固定されているのではなく、
流れのなかで均衡を探しつづけています。
そのリズムに抱かれながら、
私たちもまた揺らぎを通して
新しい調和を学んでいくのでしょう。

参考・典拠
アンリ・ベルクソン『時間と自由』(1889)― 「持続」概念、自由の定義
アンリ・ベルクソン『物質と記憶』(1896)― 記憶と脳の関係
アンリ・ベルクソン『意識に直接与えられたものについての試論』(1889初稿)― 質的時間の区別
アンリ・ベルクソン『笑い』(1900)― 社会的リズムと均衡の回復

イズモアリタ(MASAFUMI ARITA)
星の神話とタロットの図象
/伝承叡智の研究
テキスタイル&グラフィック
/デザイナー
プロフィール:
星とタロットの図案家として 未発掘の心象シンボルと無意識の同時代カルチャーをスケッチしている。2004年より世田谷ものづくり学校にアトリエを構え、コンバースシューズやヤコブセンのチェアをはじめ、BEAMS、IDEE、CIBONE、サザビー、ほぼ日、JTB、伊勢丹BPQC、高島屋、等で様々なプロダクトを発表してきた。近年は、独自の縄文&出雲的な感性と星々との呼応から制作活動を展開。古代の伝承から同時代のものまで古今東西の文化に詳しく、ゼロ歳からのワークショップ、美術大学で造型指導も行っている。
イズモアリタ instagram
@izumoarita