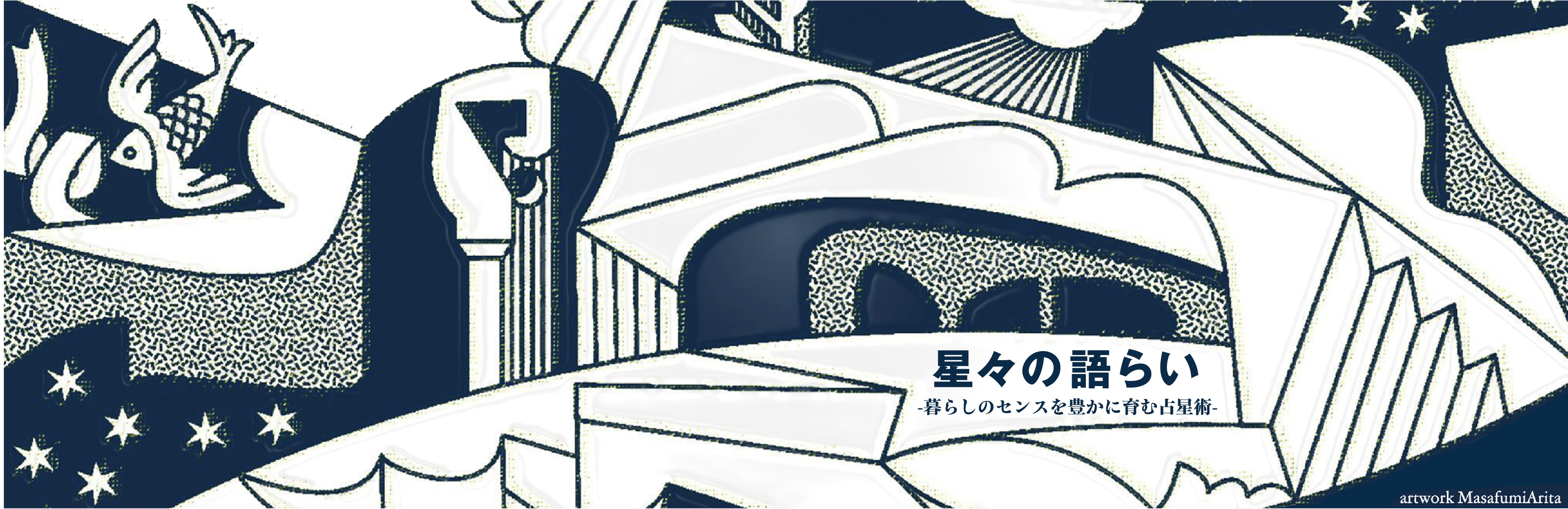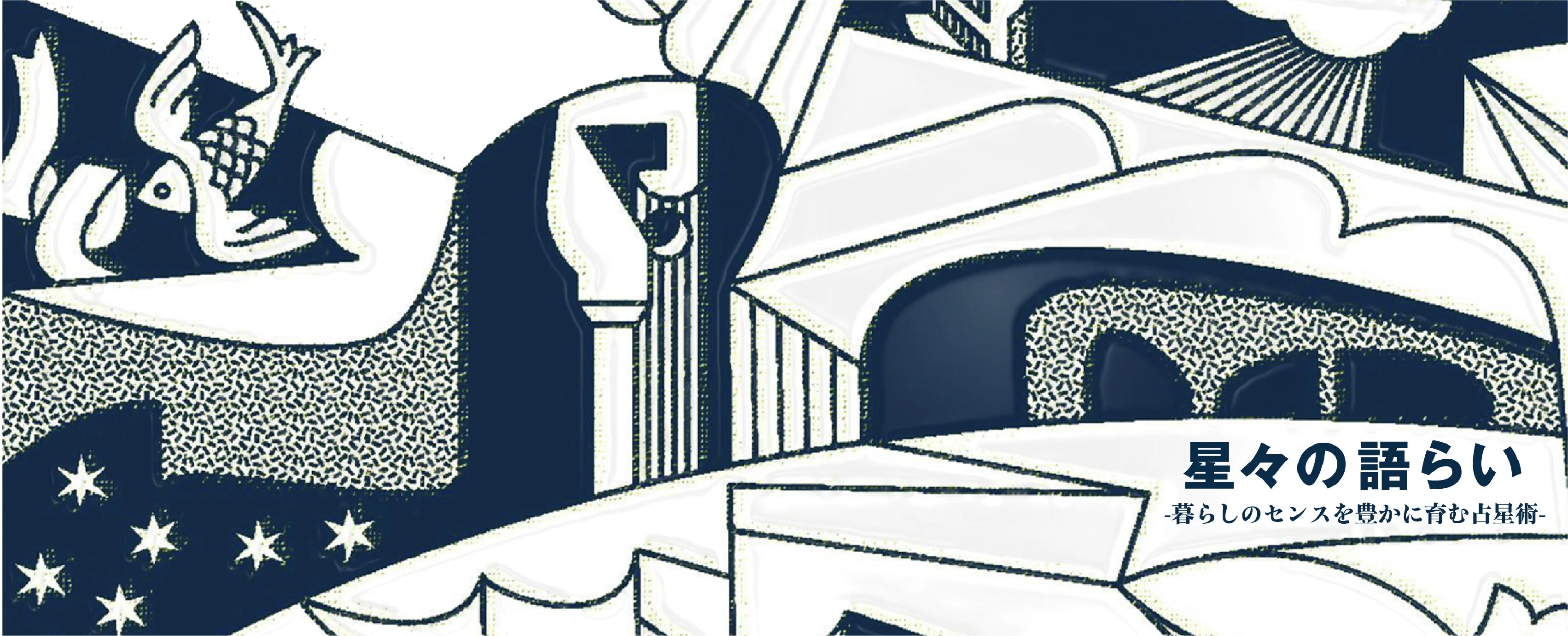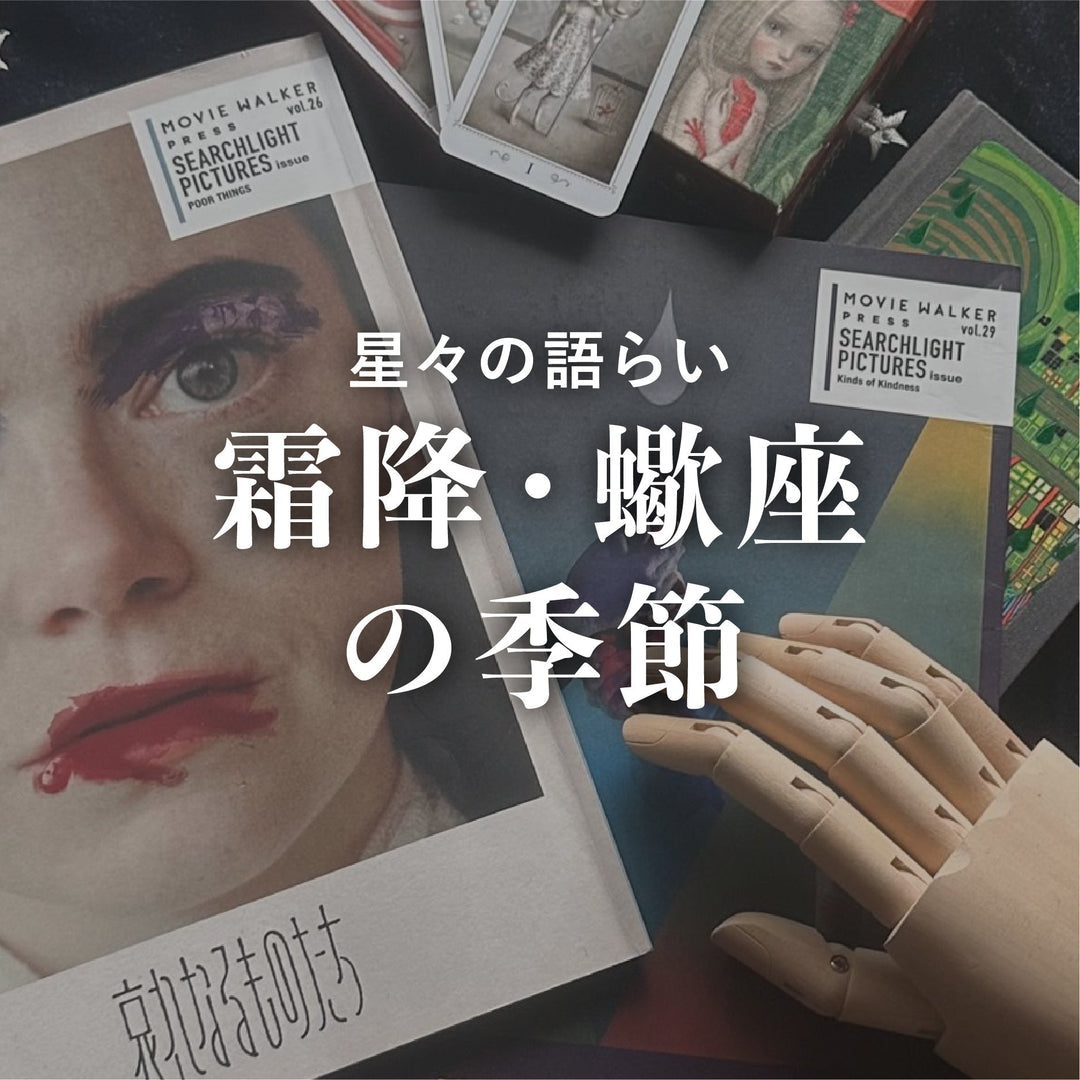INTRODUCTION
星に夢中になり始めたのは14歳のころ、当時(1980年)手描きで作成したホロスコープを眺めては、惑星が示す意味と同時代の出来事との共時性にワクワクしていたのを覚えています。
そのときの天体配置で特に印象的だったのは土星と木星が共に乙女座から天秤座に移動して約600年ぶりに風のエレメントに集っていたこと。
いまでは多くの人が耳にする「風の時代」へのストロークを感じながら未来の私らしい在り方を模索していました。
そこから半世紀近い月日を経た現在、新しい時代の到来は外からもたらされる以上に、個々の内なる気づきと豊かな繋がりから拡がっていくのだと実感しています。
この連載では、惑星たちが奏でる二十四節気ごとの天体配置から、より魅力的で私らしい暮らしを楽しむための星々の語らいをお伝えしていきます。
大暑・獅子座の季節
太陽が獅子座にイングレスするこの日、大地は熱気をたたえ、
光はまっすぐに、私たちの意志の輪郭を照らそうとしています。
その熱は、ただ外界を灼くためのものではなく、
私たちの内側に眠る「まだ名づけられていない何か」に火をともすような、
内なる創造の季節の始まりです。
内なる太陽をめぐる問い
自己とはなにか。
自我とはどう違うのか。
惑うことのない“真の意志”とはどこから生まれるのか。
日々の対応や過去の思い込みから解放された『私』とは?
こうした問いは、獅子座に象徴される「自己の中心にある太陽」をめぐる探究でもあります。
意志とは、何かを選び取る力でありながら、
しばしば環境や感情、過去の記憶によって曇らされてしまいます。
けれどもユングが述べたように、意志や自己とは単なる自我の産物ではなく、
むしろ集合的無意識や魂の深層とつながる“内なる太陽”としての働きなのかもしれません。
惑いとは、方向感覚の喪失であり、意味の消失でもあります。
けれどそこからこそ、本来の自己に触れる旅がはじまる。
「惑う」という語の背後には、星(planet)と心(psyche)の共鳴が感じられます。
獅子座に宿るのは、周囲を照らす“意志の輝き”。それは、派手さや自己主張ではなく、
自分自身の意志を誰よりも信じて燃やし続ける、そんな静かな火の強さが備わっているようです。
では、私たちはこの“意志”を、どのように星々の名に託してきたのでしょうか。
惑星とは──私たちの心と宇宙の間を行き交う、もうひとつの言語だったのかもしれません。
私たちがよく耳にする「惑星」(planet)という言葉。
英語の「planet(プラネット)」は、古代ギリシャ語で「さまよう者」を意味し、
17世紀の中国で「惑星」と漢訳されました。
ここで興味深いのは、西洋の “星が彷徨っている” という語感に対して、
東洋では “星が人の心を惑わす” と感じとられていたということ。
この「惑星」という言葉を江戸時代の日本に伝えたのが、
獅子座生まれの本木良永(1735年7月30日)です。
彼はオランダの天文書を翻訳し、
地球が太陽の周りを回る地動説や宇宙の広さを紹介しました。
「他の星にも生命がいるのかもしれない?」
獅子座らしいロマンで、星空に新しい物語を紡ぎだす
きっかけを生み出した人物です。
2025年7月22日 大暑図

この日のチャートには、創造と変容が呼応し合う複雑な響きが宿っています。
獅子座0度に入ったばかりの太陽は4ハウスの深部で、
12ハウスの土星・海王星とトライン(120度)の調和を結びながら、
5ハウスに向かって光を放っています。
この12ハウスは、獅子座生まれの心理学者カール・グスタフ・ユングが語った
「集合的無意識」や「魂の奥底にひそむ象徴の海」を想起させます。
春分点近くの牡羊座の土星と海王星の連携によって、
これまで意識化されていなかった事柄に確かな輪郭が添えられていきそうです。
月が象徴する“自我”や“群衆心理”は敏感に反応し、
太陽の意志は無意識の深みと対話しながら“新たな創造的意図”を表現し始める。
この魚座の土星と海王星が乙女座の火星・双子座の金星のスクエアに関与しているのも印象的です。
そこに浮かび上がるのは、実利や管理と自由な感性との対峙。
次世代的な表現に移行していく際のプロセスを象徴しているようにも見えます。
11ハウスの冥王星と太陽はオポジション(180度)。
個の表現(4ハウスの太陽)と、集合的無意識の変容(冥王星)の間に緊張が生まれています。
その間を2ハウスの天王星がセクスタイル・トラインで調停する構図は、
新しい技術や同時代の価値を通して、個人と社会の橋を結び直す働きを暗示しているようです。
導きの光としての太陽
今回の大暑図で、最も注目すべきなのは、天王星・海王星・冥王星という三つのトランスサタニアンが、
セクスタイルとトラインで相互に絡みあっていることです。
惑星が「惑う」のか、それとも人間が「惑わされる」のか。
「地球の視点」を超えた「太陽の視点」に立つならば、惑って見える錯覚領域からの脱却もあり得る。
天動説から地動説へと移行した時のように、
太陽からの視点や、太陽系内の相対的な視点、さらには量子的な見解へと、
無意識の意識化と新しい言語的な創造行為が予感されます。
私たちは、自らの惑いを引き受けながら、
新たな宇宙との関係を模索しているのかもしれません。

『医家先哲肖像集』1936年 藤浪剛一 / 刀江書院

イズモアリタ(MASAFUMI ARITA)
星の神話とタロットの図象
/伝承叡智の研究
テキスタイル&グラフィック
/デザイナー
プロフィール:
星とタロットの図案家として 未発掘の心象シンボルと無意識の同時代カルチャーをスケッチしている。2004年より世田谷ものづくり学校にアトリエを構え、コンバースシューズやヤコブセンのチェアをはじめ、BEAMS、IDEE、CIBONE、サザビー、ほぼ日、JTB、伊勢丹BPQC、高島屋、等で様々なプロダクトを発表してきた。近年は、独自の縄文&出雲的な感性と星々との呼応から制作活動を展開。古代の伝承から同時代のものまで古今東西の文化に詳しく、ゼロ歳からのワークショップ、美術大学で造型指導も行っている。
イズモアリタ instagram
@izumoarita